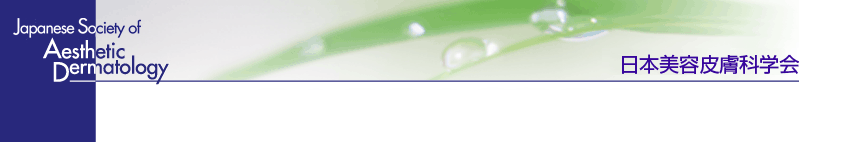一般社団法人日本美容皮膚科学会
理事長 須賀 康
この度、2023年8月19日に東京都、新宿にて開催された社員総会の議を経て、一般社団法人日本美容皮膚科学会の第11代目の理事長を拝命しました。本学会は1987年、日本美容皮膚科研究会(会長:故 安田利顕 先生)の発足を嚆矢としておりますので、すでに35年の歴史があります。また、総会員数は2023年8月現在で3,000名を超えるまでに成長しており、昨今の本邦における美容皮膚科の隆盛を反映するものとなっています。このタイミングでの理事長就任は、今後の更なる学会の発展を託されたという意味で、改めて責任の重さに身の引き締まる思いです。立ち止まらず、常に今より一歩前へと踏み出し成長する『不断前進』の気概を持って邁進したいと思います。
私は学会としては第5代目の理事長にあたる古川福実 先生より第32回日本美容皮膚科学会総会・学術大会(2014年、千葉県、浦安市)の大会長を拝命して、本学会の運営に携わる様になりました。その後を引き継いだ坪井良治 理事長の元では、美容皮膚科の医療安全、リスク回避の要となる、総合補償制度を創設する仕事に携わるために本学会理事会に新設された保険委員会の委員長として理事に就任させて頂きました。この制度はそれ以後の川島眞 理事長、川田暁 理事長の元では会員数も大幅に増えたこともあり、現在では一般社団法人日本美容医療リスクマネジメント協会(理事長 坪井良治 先生)へと発展しています。その後の森脇真一 理事長の元では、新型コロナウイルス感染症の蔓延下で本学会や美容医療のあり方を模索することになり、私も本学会の理事会、代議員会での取り決めの透明化、健全化の仕事に携わりました。とくに前任の第10代の山本有紀 理事長の元では、推薦委員会における新入会員の迅速な審査、手続きを行なうための制度改革に携わり、この1年間は副理事長として様々な課題に関わり取り組んで参りました。
今後、理事長としての私の抱負は学会員の共通の願いでもある『美容医療が誰からも信頼される医療となる』ことを最終目標として、歩むべき方向を考えて行きたいと思います。すなわち、学会の約款にもある様に本学会の活動目的である1)「美容皮膚科学に関する研究、及びその研究成果の普及」につとめて、美容医療が目覚ましく進歩して新知識・技術も増える中、何処と無く付いて回る胡散臭いイメージを払拭したいと考えています。
また、その為には2)「美容皮膚科医療の質の確保」をすることが大切です。すでに当学会の入会規定では専門医機構の定めた基本19領域に所属している医師に新規加入して頂くことになっており、根拠のある標準治療をしっかりと学んだ医家が、更に総会・学術大会の講演や機関誌Aesthetic Dermatologyの特集などを通じて美容皮膚科を学ぶことを推奨しております。皮膚科専門医を取得後のサブスペシャリティーとしての美容皮膚科医の育成を担っている日本皮膚科学会の美容皮膚科・レーザー指導専門医委員会に対しても、全面的にご協力したいと思っています。
更に美容皮膚科医療において不注意な有害事象、合併症が発生しないように、3)「医療安全、リスク回避の啓蒙と教育」も大切です。これには本学会の保険委員会が中心となって総会・学術大会、機関誌などでの企画を工夫するなど、教育体制の充実や学問研究の一助となるように理事会内での連携を強化して参りたいと思います。
以上、就任にあたり、ご挨拶と所信を述べさせて頂きました。先述の如く、本学会では会員数が着実に増えておりますが、皮膚科医、形成外科医以外の診療科からの入会希望者が年々増加しており、その為に舵とりが益々難しくなってきていると言えます。理事を中心とした各種委員会がその機能を存分に発揮できる雰囲気を作り、本学会のさらなる発展につなげたいと思います。また、従来通り、総務委員会(委員長 尾見徳弥 先生)が中心となって会員の皆様からも学会の活性化に向けたご提案を広く受け付けております。これからの在任期間中は会員の皆様方からの温かいご指導、ご鞭撻をいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
|